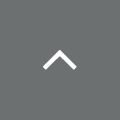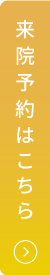出産・授乳を経て卒乳後、鏡を見るたびに自分の胸が変化したことに戸惑いを感じる方は少なくありません。
「しぼんだように見える」「垂れてきた気がする」「左右で差が出てきた」など
授乳を終えた多くの女性が、胸にまつわる悩みを抱えがちです。
その背景には、ホルモンバランスの変化や靭帯の緩みといった身体的な要因だけでなく、普段の姿勢や下着の選び方などの生活習慣も影響しています。
この記事では、卒乳後の胸に起こる代表的な変化の理由をはじめ、自宅でできるケアや美容医療の選択肢までを幅広く紹介します。
卒乳後に起こる胸の変化
卒乳後の胸は、授乳中よりサイズが小さくなったり、位置が下がったように見えたりと、さまざまな変化が起こりやすいです。
授乳中に発達していた乳腺は、役割を終えることで自然に萎縮し、バストのボリュームが減少していきます。
それに伴って皮膚のハリが失われ、たるみが目立ちやすくなることもあります。
また、胸を支えるクーパー靭帯が妊娠中や授乳中に伸びてしまうことで、元の位置に戻りにくくなるのも一因です。
こうした変化は誰にでも起こりうるものであり、正しい知識を持って向き合うことが大切です。
卒乳後の胸の変化|垂れ・萎み・左右差を引き起こす4つの原因
卒乳後の胸が変化する背景には、次のようにいくつかの要因があります。
乳腺の萎縮|バストのボリュームが減少
授乳を終えた後の乳腺は、使われなくなることで徐々に萎縮していきます。
その結果、バスト全体のボリュームが減少し、しぼんだような印象を受けることがあるでしょう。
もともと胸のサイズが大きかった方ほど 程、変化を大きく感じられる傾向があります。
クーパー靭帯の伸び・損傷|胸の位置が下がる
バストの「ハリ」を支えているクーパー靭帯は、妊娠や授乳によってサイズが変化することで伸びたり損傷したりすることがあります。
一度伸びてしまった靭帯はもとに戻りにくいため、バストの下垂やハリの低下を感じてしまうでしょう。
ホルモンバランスの乱れ|皮膚のハリが失われる
卒乳後は、女性ホルモンの一種であるエストロゲンの分泌量が減少します。
エストロゲンは、肌のハリや潤い、弾力を保つ働きがあるため、分泌量の減少によってバストを含めた全身の皮膚もたるみやすくなります。
生活習慣の乱れ|姿勢や下着が形崩れを招く
猫背などの姿勢の乱れや、ブラジャーを装着せずに過ごす時間が長くなること、サイズの合わないブラジャーを装着してしまいがちなことも、胸の位置や形に影響を与えると考えられます。
授乳中はバストサイズの変化に対応できていない下着を使い続けていた方もいるでしょう。
これらがバストの形を崩してしまう原因になることがあります。
自宅でできるセルフケア4選
卒乳後のバストの変化は、日々のセルフケアで和らげる可能性があります。
次の4つのセルフケアを生活の中に取り入れ、継続してみましょう。
卒乳後のバストケアは、日常生活の中に取り入れやすい方法から始めるのが現実的である。
姿勢を正す|猫背を改善して胸の位置を高く見せる
背中が丸まっていると、バストが下がって見えます。
猫背になりがちな方は、日常的に姿勢を正す意識をするだけで、印象を変えられるでしょう。
大胸筋のトレーニング|卒乳後のバストアップ筋トレ
バストの土台を支えている「大胸筋」を鍛えることも大切です。
合掌のポーズや軽めの腕立て伏せなどで大胸筋を刺激して、バストの土台を整えましょう。
<合掌のポーズのやり方>
1.背筋を伸ばして椅子に座る、または立った状態で行う
2.両手のひらを胸の前で合わせる(合掌の形)
3.肘を肩の高さに保ち、両手を押し合うように力を入れる
4.そのまま5〜10秒キープする
5.力を抜いて休憩し、これを数回繰り返す
合掌のポーズは、テレビを見ながらでも気軽に行えます。
時間や負担をかけずにトレーニングを始めたい方は、このトレーニングからはじめてみましょう。
入浴中に優しくマッサージ|卒乳後バストマッサージで血行促進
湯船につかり体が温まっているタイミングは、血行が良くなるためマッサージに適しています。
胸全体をやさしく円を描くようにマッサージすることで、ハリ感アップやリラックス効果も期待できます。
サイズの合ったブラジャーの着用|型崩れを防ぎ美しいシルエットに
授乳中のブラジャーをそのまま使い続けている方は、現在のバストサイズに適するブラジャーに買い替えましょう。
下着店などでフィッティングを受け、今の自分に合ったブラを選ぶことで、型崩れを防ぎながらシルエットも美しく見せられます。
これら4つを完ぺきにこなそうとせず、できることから習慣化していくことが大切です。
しかし、卒乳後のバストケアにおいて、自宅でのセルフケアだけでは限界があることも事実です。
一度伸びてしまったクーパー靭帯は、ストレッチやマッサージでは元の状態に戻せません。
著しく失われたボリュームや皮膚のたるみに対しても、トレーニングだけで根本的な改善を図るのは難しいでしょう。
美容医療という選択肢|豊胸手術はいつから受けられる?時期と注意点
卒乳後のセルフケアだけでは理想に近づけるのは難しいと感じている場合、美容医療を取り入れることで短期間でも変化を感じられるアプローチが可能です。
自然な仕上がりや見た目の左右差の改善を求める方にとって、豊胸手術は有効な選択肢の一つといえます。
実際に、ミセルクリニックでも卒乳後の悩みから豊胸手術を検討・実施される方が多く、数多くの症例があります。
ここからは、豊胸手術の種類と受けられる時期や注意点について説明します。
シリコンバッグ豊胸
シリコンバッグ豊胸とは、体内にシリコンバッグを挿入し、即時的にボリュームアップを実現する方法です。
はっきりとしたサイズアップを希望する方に適しています。
シリコンバッグ豊胸は一度の手術で大幅なボリュームアップを実現できること、左右差などの悩みにも対応できることが利点です。
一方で、一般的には10年程度でシリコンバッグの交換が必要になる点に注意が必要です。
脂肪注入豊胸
脂肪注入豊胸は、自身の脂肪を吸引・加工して胸に注入しバストアップを図る方法で、自然な触感と見た目を重視する方に好まれやすいです。
この施術は、バストアップと同時に部分痩せにも効果的なことや、脂肪が定着すれば長期的に効果が続くというメリットがあります。
一方で、注入した脂肪の一部は吸収されてしまうため、期待したようなバストアップ効果が得られないこともある点に注意が必要です。
どちらの方法を選択するにせよ、医師とのカウンセリングや相談は欠かせません。
自分の体型や希望に合った施術を選択できるよう、しっかり相談できるクリニックを選択するようにしましょう。
豊胸手術が受けられる時期は
卒乳後すぐに豊胸手術を受けたいと考える方もいるでしょう。
しかし、授乳を終えた直後の体はホルモンバランスが不安定なため、しばらく期間をおいてから手術を受けることをおすすめします。
具体的には、卒乳から6ヶ月以上が経過し、胸の状態が安定してからの施術が望ましいとされています。
医師の診察によって、皮膚の状態や回復状況を確認して、適切なタイミングを見極めてもらいましょう。
また、施術後に出産・授乳を考えている方は、術式によって授乳機能に影響が出ることもあるため、事前の相談が必要です。
よくある質問(FAQ)
卒乳後の胸はどれくらいで元に戻りますか?
個人差はありますが、卒乳から半年ほどでホルモンバランスが安定し、胸の状態も落ち着いてきます。ただし、妊娠前とまったく同じ状態に戻ることは難しい場合があります。
卒乳後の胸を自宅でケアする方法はありますか?
姿勢を正す、大胸筋を鍛える、入浴中のマッサージ、サイズの合ったブラジャーを着用するなどが有効です。毎日の小さな習慣を積み重ねることが大切です。
卒乳後すぐに豊胸手術は受けられますか?
授乳直後はホルモンバランスが不安定なため、卒乳から6か月以上経過して胸の状態が安定してからの施術が望ましいとされています。
卒乳後の胸の垂れやしぼみは完全に改善できますか?
セルフケアである程度和らげられますが、伸びたクーパー靭帯や大きく失われたボリュームを元に戻すのは難しいです。美容医療を組み合わせるとより大きな改善が期待できます。
痩せ型でも脂肪注入豊胸はできますか?
BMI18程度あれば多くの方が対象になります。極端に痩せている方は脂肪が採れにくいため、カウンセリングで適応を確認しましょう。
卒乳後の胸には無理なく適切な方法で向き合おう
卒乳後の胸の変化は、妊娠・出産・授乳という大きな役割を果たした体の自然なプロセスです。
体がきちんと機能し、命を育んだ証ともいえるでしょう。
急激なバストの変化に驚いたり、体に違和感を抱いたりすることも、ごく自然な反応です。
バストの変化が気になる方は、生活習慣を見直し、自分なりにできるセルフケアから取り組んでみましょう。
それでも気になる場合や、自力ではどうにもならないと感じる場合には、美容医療という選択肢を前向きに考えることも一つの手段です。
ミセルクリニックでは、卒乳後のバストに関する悩みにも丁寧に寄り添い、自然な仕上がりを目指した施術の提案を行っています。
まずはお気軽にご相談ください。
監修

奥立 大樹
ミセルクリニック大阪梅田院院長
脂肪吸引や脂肪注入豊胸をはじめとする美容外科施術では、理想に近づけるだけでなく、体への負担を抑えることも大切です。仕上がりの美しさはもちろん、安全性や術後の回復にも配慮し、設計段階から一人ひとりと丁寧に向き合うよう心がけています。
美容医療は、外見の変化だけでなく、人生にも大きな影響を与えます。だからこそ、納得のうえで手術に臨んでいただきたいと考えています。後悔のない選択のため、医師としての信念を持って、分かりやすく正確な情報をお届けしています。